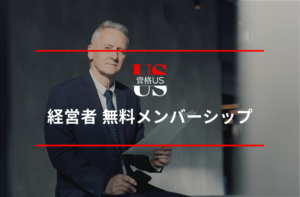アメリカで就職し
世界で通用する人材へ
夢を
私たち資格USは、アメリカに”目的”を持ってくる人たちや、 ”夢”を追いかける人達を応援するサービスを提供します。 アメリカで働くという事を難しく考えていませんか?
将来アメリカで働きたい!という夢を諦めないでください。
私達が全力でサポートします!
資格US
メンバーシップ
アメリカに進出したい皆さんを応援したいという思いから始めたオンラインサロン。資格USでは、「アメリカで働きたい」、「アメリカで今の技術を活かしたい」、「アメリカでビジネスを始めたい」、「アメリカに支社を作りたい」といった日本の方々のビザや就職、ライセンス、会社設立/ビジネスプラン等でサポートさせていただきます。資格USオンラインサロンでは、最新のアメリカ就職、ビザ/ライセンス関連情報、経営者向け情報などをリリースしていきますので、ぜひご参加ください。
資格やビザのこと、ご相談ください!
アメリカで働くことを難しいと思っていませんか?準備や書類集めなど色々と手間なことはありますが、ぜひ資格USにお任せください。資格やビザ取得、就活アドバイザーとして様々な業種の方をサポートしております。
お問い合わせ
資格USでは、アメリカで働きたい方と専門性の高い人材を雇いたい企業のマッチングを提供しています。アメリカでビザを取得するのはかなり難しいと思われがちですが、ビザサポートしてくれる会社はゼロではありません。アメリカの中には、人手不足のためビザを出してでも日本人に来てほしいという企業も多々存在しています。
アメリカで専門職として就職したい方、アメリカでグリーンカードを取得したい方、アメリカで会社を経営したい方は、電話、メールによる初回相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。